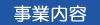米国ボストン報告 アメリカから見た世界(植田 麻記子)
「ポスト3.11」に生きる (2011.11.25)
2011年3月の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)についての報道は、米国でも次第に減少しています。関心の持続の難しさを実感します。一方で、現状を知りたいという人も少なくありません。震災以降、日本は世界中から様々な形で、多くの支援、援助を受けています。先ず日本人として、関心を持ち続け、考え、自分なりの言葉で、語ることが求められます。
そうした中、米国でも、支援を継続しながら、様々な形で活動報告を発信するボランティアの人たちから話を聞く機会を得ます。そこで指摘された課題の一つは自殺の増加、そしてもう一つはボランティアの数の少なさです。ボランティアの数については阪神淡路大震災時に比べ、かなり被災規模が甚大であったため、ボランティア希望者も、当初、どこにどのように行き、活動に参加すればよいのか分からなかった点、また日帰りでの活動が困難であることも原因として指摘されます。いずれも長期的に取り組まなければならない、重大な課題です。
一方で、結婚率の増加などに表れたように、震災が人々の意識に与えた影響も中長期的に、捉える必要があるでしょう。地震および津波の被害の衝撃は、センセーショナルな映像とともに人々に大きなショックを与えました。被害は震源地に近い岩手、宮城、福島の東北三県から、茨城、千葉の関東二県を中心に広域に広がり、埋め立て地の液状化も深刻な問題となりました。首都東京では、地震発生当日に大量の帰宅困難者を出し、非常時の都市機能が試されました。福島第一原子力発電所の事故は放射能による食品汚染、電力不足、原発の是非をめぐるエネルギー問題へと発展しました。人々はこれまで享受してきた安全な日常生活が極めて脆弱なものであることを知りました。とりわけそれは若者たちの感受性に、どのようなインパクトを与えたでしょうか。そしてそれは、ポスト・3.11の世界にどのような道を開くでしょうか。
ボランティアの方が指摘された「個の物語」が埋没する懸念に、そのカギがあると思います。政治を中心に、被災状況を俯瞰し、復興の舵を取る強いリーダーシップが求められると同時に、一方で、そこに関わる人の数だけ存在する「個の物語」への視点から、動き続ける社会の姿を捉える眼差しも忘れてはいけないでしょう。そして、実際に被災地に個人として入り、活動し、その活動をアウト・プットするボランティアこそ、その「個の物語」を語り継ぐことのできる存在であり、そこに一つボランティアの大きな意義があると考えます。出張美容室、子どもたちに本を届ける文庫づくり、思い出の品の保護と、多くの若者たちが、それぞれの能力を生かして、それぞれの視点からアイディアを出し、組織を作り、現在ボランティアとして活動しています。(関連資料1)
大人になる子ども、続く物語
現在の若者の人間関係が希薄というのは、表層的な理解だと思います。私たちの世代は、「個の物語」の多様性をよく理解しています。価値観、趣味趣向、生き方、働き方、家族の形、恋愛の形、多岐にわたる「個の物語」にとても敏感です。その前提に他者との関係を築こうとするのです。様々な思い込みや決めつけが相手の、そして自分の「個の物語」を簡単に傷つけてしまうことを知っています。それは、傍からみれば傷つきやすい脆弱なものに見えるかもしれません。けれど、被災地でのボランティア活動にも見られるように、地道な取り組みによって、「個の物語」に寄り添った強い絆を、作ろうとしています。震災によって従来のコミュニティーが崩壊した社会で、あるいはポスト・モダンの社会で、人と人が繋がるということはそういうことなのではないでしょうか。実際にはうまくいかないこともあります。それは、時にまさに「壁」に「卵」を投げ続けるようであり、ここに村上春樹が描くヒーロー像への共感があるのだと私は思っています。
震災を長期的な視点で捉え、「個の物語」を語る一つの方法は、アートです。ここではアートを、個別的な経験や感情を、普遍化かつ抽象化することで、他者の琴線に触れる表現として提示する様々な活動と理解したいです。映画もその一つです。映画『その街の子ども』は阪神・淡路大震災15年の節目に、NHKが作成した特集ドラマを下に作成され、2010年に公開された映画です。被災の体験と記憶を抱えて大人になり、東京に住み、それぞれの思いから「その街」(神戸)に戻り、ふとしたことから出会った若者、勇治と美夏のやり取りの中から、次第に二人の「個の物語」が語られます。本作はドキュメンタリーの形式を取り入れた編集を取っていますが、とても魅力的なのは、そこには「震災」だけでなく、今を生きる若者の等身大性があるからだと思います。互いの「個の物語」を、不器用ながら次第に語り合うことで、他者との関係を築く若者の姿があります。(関連資料2)
「Tokyo」
街に生きる若者たちは、ポスト・3.11をどう生きていくのか。「Tokyo」を舞台に、その一面を切り取ったドキュメンタリー、『Tokyo Rising』はアートの観点からポスト・3.11の若者たちの世界観を提示しています。米国の音楽プロデューサーであるファレル・ウィリアムス(Pharrell Williams)がホストを務め、3.11後の東京を紹介する本作には、世界が描く「Tokyo」の一つのイメージがあります。それは、様々な感性が一緒に存在する、少し不思議だけれどもクールな現代都市です。地方から、あるいは世界から東京に集う若者は、寄る辺なき存在ゆえに、「個の物語」を語り、表現する場を求め、出会い、自己と他者の肯定的関係を築きます。それは他者が他者として共存できる多様性の街を作っています。
自己表現の最も身近な手段であるファッションを始め、音楽、ダンス、絵画、あらゆる創作活動で、若者のクリエイティビティは、ポスト・3.11を一つの解放として捉えています。本作の中で語られる、3.11によって「謎の予定調和」が崩壊し、そこで理解したことは「大人」も(自分たちと)同じ「人間」であったということだったという言葉が印象的です。享受してきた安全な日常生活は、震災が起こるまでは自分たちの上の世代によって作られた、「謎」めいた「予定調和」であったが、それが壊れた今、それは謎でもなんでもなく、「失敗」も含めて自分たちと同じ人間である「大人」が作ってきたものであったということに気づくのです。
それは発達心理学でも指摘されるように、親を乗り越え、子が自立する成長過程で本来自然なことです。社会の世代間にも当然不可避の段階ではないでしょうか。「子」のこの発見は「大人」にとって、確かに恐怖です。しかし、そこに必要なのは「大人」の若者への信頼だと思います。それは、若者の能力に対する信頼と同時に、若者との関係性そのものへの信頼性です。若者たちは「大人たち」の「失敗」を知っても、その物語を全否定することはありません。なぜ、「大人たち」がそのような選択をしたのか、その中で偉大であった判断は何であったか、犠牲にされたものは何であったのかを知りたいと思い、また十分に理解することができます。その対話の上に、若者たちのリーダーシップによるポスト・3.11の日本があるのではないでしょうか。
「完璧な大人たち」の喪失によって、解放された若者たちは、個々の能力を発揮できるポスト・3.11の世界に、失ったものの大きさに震えながらも、不安に勝る期待を込めて「昇る東京」、「昇る日本」の未来を見ているのではないでしょうか。それはカウンター・カルチャーという観点に留まらず、価値観が多様化した社会における政治活動・経済活動・文化活動、あらゆる側面において、様々なクリエイティビティとアイディアを提示しています。(関連資料3)
関連資料1:United Planet HP
関連資料2:映画『その街の子ども』HP
関連資料3:『Tokyo Rising』 HP