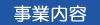米国ボストン報告 アメリカから見た世界(植田 麻記子)
ゴードンさん訃報で、フェミニズムを考える (2013.5.31)
基本的人権としての両性の平等
昨年末、ベアテ・シロタ・ゴードン(Beate Sirota Gordon)さんが亡くなりました。アメリカで舞台芸術監督、フェミニストとしても高名な彼女は連合軍総司令部(GHQ)の要請で日本国憲法の作成に携わり、人権条項の制定、とりわけ新憲法に男女平等の精神を盛り込んだことで知られ、その訃報は日本でも大きく取り上げられました。今回は、彼女を手掛かりに、フェミニズムについて、少し考えてみたいと思います。
先ず、簡単に彼女の来歴についてご紹介したいと思います。彼女は、ロシア出身のピアニストであった父レオ・シロタと母オーギュスティーヌとともに来日し、幼少期を日本で過ごすことになります。ユダヤ人であった両親はロシア革命に伴うユダヤ人排斥によってオーストリア国籍となるものの、ナチスの台頭を背景とした反ユダヤ主義により、ヨーロッパに戻ることが困難となり、家族は長く日本に滞在することになりました。母親によって、ベアテは幼い頃より英語とフランス語を学びました。そして、両親は、ベアテをカルフォルニア州サンフランシスコ、オークランドのミルズ・カレッジへ留学させることを決め、ベアテは渡米します。東京音楽学校での教えていた父は、日本に残ることを決め、ベアテは両親と離れたまま、日米開戦を迎え、親子は互いに消息をつかむことも難しい状況が終戦まで続くことになります。なお、ベアテはミルズ・カレッジ在学中に当時の学長であったオーレリア・ヘンリー・ラインハートにフェミニズムの影響を受けたと言われます。
両親に経済的支援を頼れない中、ベアテはサンフランシスコのCBSリスニング・ポストで日本からの短波放送の英訳のアルバイトをし、経済的自立を図りました。その後、戦局が進み、放送局が政府の管轄に編成される中、ベアテは米連邦通信委員会の対外放送の部署で働くことなります。何とか、日本からの情報を集め、家族の安否を知ろうとする当時の緊迫した日々について、ベアテは自伝の中で触れています。大学卒業後、戦争情報局での仕事を経て、間もなく叔母を頼ってニューヨークに移ったベアテはタイムズ誌に職を得ます。ここでベアテは根強い女性差別を経験することになります。
職場の同僚の助けも得て、日本の両親の消息をようやくつかんだベアテは、GHQの民間人枠の研究員として職を得て、再び日本の土を踏むことを決意します。これまでのキャリアと、日本語を含む六カ国語に上る語学の能力を買われ、ベアテはGHQの新憲法起草に関わることになります。ベアテは人権小委員会に入り、社会保障と女性の権利について作成しました。ベアテの女性の権利に関する条項は合衆国憲法にも明記されていない急進的なものであり、そのまま採用されることはありませんでしたが、従来の家制度を否定し、結婚及びそれに基づく家庭における個人の尊重、両性の平等な関係性の規定(日本国憲法24条)に生かされることになりました。
初期の占領政策では、民政局(GS)を中心に、社会民主主義的な理念を持った多くのニューディーラーがリーダーシップを発揮しました。ベアテだけでなく、GHQ内部には、新生日本にアメリカ本国で未だ実現されていない、あるいは、挫折しかけている理想を込めようとするエネルギーに溢れていました。実際、敗戦は、少なからずの国民にとっても絶望感よりも、むしろ戦時中の困窮と抑圧からの解放感を与えていました。言論の自由を取り戻し、「戦後民主主義」に沸く中、紙、インク、物資の不足する中、カストリ雑誌の出現に象徴されるように、人々は政治から娯楽に亘るまで貪欲に活字、そして新しい価値観を求めたと言われます。日本政府、GHQだけでなく、民間人からも新憲法案が提示され、主権在民を支柱とする日本国憲法を基盤とする戦後日本の再建をめぐり、当時、日本国内外、そして上から下からの普遍的な理念を追求する理想主義的な気運が日本社会には広がっていました。ベアテもまた、そこにフェミニストとして強い使命感とともに立ち会ったと言えるのでしょう。
ベアテはその後ニューヨークに戻り、アジア・ソサエティおよびジャパン・ソサエティなどを拠点に、世界の民俗芸能を米国社会に紹介する事業に、舞台芸術監督として、長く携わりました。
【参考】
「映画『ベアテの贈り物』(2005年4月公開)」
「Middlebury University でのベアテによる講演、「The Only Women in the Room」(2007年4月)[http://www.youtube.com/watch?v=TceZiTqyZXI]」
Beate Sirota Gordon, The only women in the room: A Memoir, Tokyo; New York: Kodansha, 1997.「Beate Sirota Gordon, The Only Women in the Room: A Memoir., Tokyo; New York: Kodansha, 1997.
フェミニズム?
さて、フェミニストと聞いて、皆様はどのようなイメージを持たれるでしょうか。実はフェミニストという言葉の使い方は、これまで、若干混乱してきました。現在では、女性の社会的地位の向上や、権利を主張する論者を指して、フェミニストと呼称しています。ですが、かつて、フェミニストとは時に男性に使われ、「女性に優しい男性」というニュアンスを持ちました。例えば、女性の荷物を持ってあげたり、女性のためにドアを開ける男性の行為をもって「彼はフェミニストね」などと、女性たちの間で好意的な意味合いを持って、使われることもありました。つまり、現在の意味におけるフェミニストとは真逆とも言える意味合いを帯びていました。日本でも、この用法が、とりわけある一定の世代、おそらく50代以上、の間で定着しているようです。1950年代以降、アメリカにおけるフェミニズムの展開の中で、次第に男女平等、及び女性の権利拡張論者をフェミニストと自称、他称するようになり、現在ではその理解が定着することになりました。
アメリカで研究をしていて実感することは、基本的にほとんどの女性研究者が広義において、女性の権利拡張を主張するという意味でフェミニストであるということです。そこには切実な気苦労があります。現在、私は、女性研究者によるソーシャル・コミュニティに参加しています。このコミュニティは博士課程に所属する若手女性研究者を中心に運営されており、MITをはじめ、ケンブリッジ周辺に所在する大学から資金が拠出されています。学生たちは資金集めについて指導教授に相談し、理解を示す教授から資金が提供され、活動が推奨されます。このコミュニティの会合では、しばしばワーク・ライフ・バランスをどうすべきか、議論されます。ワーク・ライフ・バランスとは、仕事と私生活のバランスをいかに図るかということですが、主に研究者としてのキャリアパスと両立させるために、どのようなタイミングで結婚し、出産すべきか、などが問題の中心になります。若手の女性研究者にとって、コミュニティはこの点において、上の世代の女性研究者のアドバイスを受けることのできる、とても有益な場となっています。そこで、常にため息混じりで会話に上がるのは、「女性が悩むほどには、男性はワーク・ライフ・バランスについて悩んでいない」という点です。
最近、アメリカの国際法、国際政治学において高名な女性研究者であるアン・マリー・スローター(Anne-Marie Slaughter)が、「やはり女性はすべてを手にいれることができないのか」、「仕事と家庭の両立は不可能だ」と問題を提起し、話題になりました。彼女は予てから希望していたように、政府で働く機会を得た際に、思春期の息子が自分を必要としていると感じ、最終的に職を離れる決断をした経緯を紹介した上で、女性にとって仕事と家庭の両立が、いかに困難であるか訴えました。実際、彼女の夫は、彼女のキャリアの充実に非常に協力的あり、支援を惜しみませんでした。彼女はパートナーの協力の重要性を強調した上で、国、社会、働き方などが変わる必要性を指摘しました。なお、彼女の夫はプリンストン大学で教鞭を執っている国際政治学者、アンドリュー・モラフチークです。刺激的なタイトルも手伝い、共感、そして「贅沢な主張だ」という反感など、彼女の論文に対する反応は様々でした。しかし、少なくとも言えることは、ベアテが日本国憲法で家庭における両性の平等を織り込んで半世紀以上が経つ今も、アメリカ、そして日本において、実際、今もなおフェミニズムの思想は絶えることなく、女性たちは挑戦を重ねながらも、ジェンダーによる負荷を感じ続けています。ですが、最後に、卑近な例をもとに、私たちの世代のフェミニズムに、おそらく起きているだろう変化に触れたいと思います。
スローター論文でも、男性の協力が不可欠であることが強調されましたが、キャリアを追求する女性たちは、現在、実際にどのようにパートナーとの関係性を築いているでしょうか。ある時、一人の男性研究者が、先に挙げた女性研究者のコミュニティについて、「魔女の集まりだね」と冗談めかしに言いました。彼は、私たちのコミュニティのメンバーのボーイフレンドでもあり、彼女もその場にいたのですが、彼の発言に、彼女も含め私たち女性研究者たちは「そうかもしれないわね」と笑って返しました。何気ない会話ですが、私はここに長いフェミニズムの歴史の中で、積極的な変化を感じることができるのではないかと思います。確かに、アメリカにおいても日本においても、とりわけ男性の中に、今なお、フェミニストに対して「男に対して神経質に目くじらを立て、血気盛んに攻撃的で、辟易するな」というようなまなざしがあります。彼の発言にもそのような視点が確かにありますが、彼がそれをジョークにしている点に着目したいと思います。そして、そのような彼の発言を愛嬌ととって、「そうよ、私たち怖い(強い)のよ」と彼女も答え、それに彼が「分かってるさ」と返すチャーミングな会話の妙があります。ここでは男女の間で、インフォーマルな場で、フェミニズムがより柔軟にとらえられていることが分かります。フェミニズムが彼らにとって、本当に男女間の対立の思想であれば、彼は自分のガールフレンドにそのような冗談を言えるはずはなく、彼女もまたそれを笑って返すことはできないでしょう。明け透けなジョークも含めて、対話が行われています。実際、彼らは共にキャリアを充実させ、彼女が忙しい際には彼が食事を作るなど、協力し合っています。家庭、パートナーシップ、最も小さく基本的な社会の中で、両性が等しく尊重し合うために必要なのは、対立ではなく、率直な対話であり、協力し合うことであるという点について、先人の努力の上に、私たちの世代は男女ともに着実に理解を深めていると言えるかもしれません。
【参考】
Anne-Marie Slaughter, “Why Women Still Can‘t Have It All.” The Atlantic, July/August, 2012.[http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2012/07/why-women-still-cant-have-it-all/309020/]