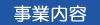第10回政策首脳懇談会を開催(2016年7月5日)
志賀俊之 ㈱産業革新機構代表取締役会長(CEO、日産自動車㈱取締役副会長)
勝又幹英 ㈱産業革新機構代表取締役社長(COO)
株式会社産業革新機構(INCJ)の果たすべき役割について
当協会は、本年7月5日(火)午前8時~9時30分頃、東京・内幸町の帝国ホテル本館『牡丹の間』にて、第10回政策首脳懇談会を開催した。今回は、日本の産業国際競争力の強化のために奮闘する㈱産業革新機構から志賀俊之代表取締役会長(CEO、日産自動車㈱副会長)と勝又幹英代表取締役社長(COO)の二氏を来賓・講師に招き、「㈱産業革新機構(INCJ)の果たすべき役割について」と題する講演を聞いた。講演では、志賀会長は、ノンコア事業を切り出し(カーブアウト)、M&Aなどを通じてグローバルなコア事業に転換、成長させる使命を熱っぽく語り、2020年頃のITによる自動車産業の劇的な変貌予測を危機感を持って説明した。また、勝又社長は、地道なベンチャー投資姿勢を強調し、日本の場合、現段階はベンチャーキャピタリスト、ファンドマネージャーなどの人材育成が急務であり、オープン・イノベーション時代だが、自前主義にこだわる経営層の弊害を突き、有機的な連携の重要性と普及を説いた。その後、協会代表者との質疑応答と意見交換を行ったが、個別の実務に関係する人達も多く、名刺交換をして後ほど対応するというケースも目立った。

講演する㈱産業革新機構の志賀俊之会長(左)と勝又幹英社長(右)
白井克彦協会会長挨拶
日本MOT振興協会は毎年約2回、政策首脳懇談会を開催している。これは、政界あるいは経済界のトップの方に講師としておいで頂き、直に懇談する機会である。去年は、政界から茂木敏充自民党選挙対策委員長にお越し頂き、色々なお話を伺うことができた。
本日は、日本の産業界の国際競争力の中核を担っている産業革新機構を代表して、志賀俊之会長、勝又幹英社長にお越し頂いた。志賀会長は、日産自動車の副会長も務められている。日本のイノベーションが盛んに叫ばれる中で、産業革新機構は、これを実現するためのひとつの大きな原動力を果たしている。最近は、小さなベンチャーをたくさん育成されているということで、日本のベンチャー育成についても非常に関心が深いところである。
志賀俊之会長
私は日産自動車の副会長でもあるが、本日は産業革新機構の会長という立場で招いて頂いた。前半は私から、産業革新機構の概要についてお話ししたい。
産業革新機構は、2009年に設立された。「オープン・イノベーションを通じて次世代の国富を担う産業を育成する」というビジョンを持ち、産業競争力強化法という法律に基づいてできた機構である。このような政府系の官民ファンドの役割は、既存の企業に対する成長投資と、ベンチャーのスタートアップのための、ベンチャーキャピタルとしての投資である。どちらにしても、結果的には企業や事業の新陳代謝を促進するという趣旨である。
抱え込み問題とカーブアウト
企業は、その中に色々な事業を抱えているが、90年代以降は「集中と選択」によりコアとなる事業とノンコアとなる事業を仕分けしてきた。しかし、残念ながら日本の企業は、あまり上手に事業の組み換えができず、結果として「選択」から外れたノンコア事業まで企業の中に抱え込んでいるのが実態である。経営の危機に瀕している会社が、潰れそうになってからノンコア事業を売却するということがよく見受けられるが、この苦し紛れの売却によって、意図しない国へ自分たちの技術を流出させてしまう状況も生まれる。「ノンコア事業であっても、それをすぐに売却することは美徳ではない」という経営者の抱え込み的な考えによって、日本経済全体が弱くなっているのが現状だ。ここで、産業革新機構の一つの役割は、ノンコアとなった事業を企業から切り出すことで、これをカーブアウトと呼んでいる。そして、カーブアウトした事業に資金投資し、ノンコアをコアにして成長させていく。あるいは、別の会社から切り出されたノンコア事業と統合して、そこに成長資金を入れ、グローバルで活躍できるコア事業にしていく。
例えば、せっかく世界に冠たる技術でもそれをノンコアに位置づけてしまうと、成長のための経営資源の配分がされない。人材や開発投資を投入しない状態の中で抱え込んでいるがゆえに、その事業は時間の経過とともにどんどん弱くなり、遂には売りたくても誰も買ってくれない状況になってしまう。例えば、私の知る限り家電をコアと言っている家電メーカーはいない。つまり、家電メーカーでありながら家電に対して投資をしてないということだ。結果として地盤沈下が進み、中国に売らざるを得なくなってしまった。中国に売ることが悪いとは言わないが、結果的に日本の技術が陳腐化してしまうことは残念である。こうならないためにも、早く、元気なうちにノンコア事業を切り出すことが大切である。その後は、この切り出したベンチャーに投資し、それを新規事業として海外に買ってもらうことで、新陳代謝を向上させようとしている。また、日本にない技術を海外から買い、その会社を日本の会社と統合して、新たなるコア事業とするケースもある。
典型的な例として、ユニキャリアというフォークリフトの会社の事例がある。私自身は日産自動車に勤めているが、ノンコアとしてフォークリフト事業を持っていた。成長投資をすることもなく抱え込んでいたところ、日立グループである日立建機のTCMというフォークリフトの会社が同じような状況にあったので、産業革新機構の投資によって、この2つを合わせたユニキャリアという会社が作られた。その後、ユニキャリアはさらにニチユと三菱重工のフォークリフト部門と統合し、世界シェア3位にまで躍り出た。
ここでのもう一つの大きなポイントは、日本の中に8社あったフォークリフトの会社が、過当競争の中で価格の熾烈な競争を繰り広げていたことである。十分な開発投資ができないがために、世界の中で付加価値あるいは技術力で勝負するということに対して、日本は弱くなってきている。例えば、自動車メーカーは日本に12社もあり、そのうち乗用車だけ作っているメーカーが8社ある。これは世界の自動車会社の約半分を占めており、このような状況の中で、技術を中心とした経営を行うことは極めて困難である。加えて、過当競争であるがゆえに低収益という問題がある。本来、ホームマーケットとは利益を得る場所で、海外の市場では、ホームマーケットで得た利益で商売を行い、市場拡大していく。しかし、日本のほとんどの産業は構図が逆である。これがゆえに円高になった瞬間に大赤字、自動車会社の大手であるトヨタでさえ2008年のリーマン・ショック以降の円高で5年間税金が納められず、単独決算は、赤字が続いた。日本で損して海外で儲かる構図が、この為替に対して極めて脆弱な産業構造を作っている。このような状況の中で再編統合を進め、先ほどのユニキャリアのようにグローバルに戦える企業を創出したい。また、ノンコアをコア事業にしていくということを、業績のひどい時期にこそやるべきだというのが持論である。
――経済同友会・資本効率の最適化委員会に基づくROEの推移、ROEと売上高の相関関係の比較などの説明があった――
自動車産業のこれから
では、現在も日本がグローバルシェア No.1の自動車業界についてである。ドイツのコンチネンタルやジョンソンコントロールズ、マグナ、ヴァレオといった世界的にも巨大なグローバルプレイヤーは今、「自動運転」や「つながる車」といった新しい開発を進めている。これに対して、日本の小さな部品メーカーは系列という名のもとに守られており、この中にいる限りは倒産することはないので、なぜ統合をしなければいけないのかという考えだ。また、日産は唯一持っている子会社を今売りに出し、大胆にも統合の布石を打とうとしているが、買いにくるのは海外のファンドばかりで日本のメーカーは誰も手を出さない。ここまで日本の経営者がリスクを取らなくなってしまったのかと思うと寂しい限りであるが、これが実態だ。現在、日本の自動車はまだシェア世界一であるが、これにあぐらをかいていられるかというとそうではない。
日本の自動車産業の強みは、工場における勤勉で真面目な労働の生産現場と、日々改善を重ねる労働の状況と日本の研究開発の存在であった。この研究開発力と優秀なサプライヤーの人々が、特に二次部品では大切である。例えば、iPhoneにおいても中身はほとんど日本製品であるように、日本の内部部品の技術力は依然として世界トップレベルである。これらのすり合わせによって、自動車のシェアは日本が依然としてトップにある。
ところが、車はこれから劇的に変わる。2050年には内燃機関がゼロになり、2030年にはガソリン車と電気もしくは水素で走る車(ゼロ・エミッション)が半分の割合で販売されるだろう。また、自動運転の車は技術的にはほぼ完成しており、現在は不慮の事故を減らすため、搭載している人工知能の機械学習を行っている段階であるので、2020年頃には実用化されるだろう。また、現在走っている車でインターネットに常時接続されている車はたった3%程度であるが、今後は車がインターネットに常時接続され、車が一つのモバイル・デバイスとなる。現在アップル社が車の開発を行っているが、これは要するにiPhoneのデバイスのような存在の車である。
こうなると、今まで我々が生産してきたような自動車のメカニカルな機械の世界が、どんどんソフトウェアに変わってくる。現在の車はハードウェアが約90%、ソフトウェアが約10%であるが、我々の見込みでは、2020年にはハードウェアが4割、ソフトウェアが6割を占めることになるので、今自動車会社は一生懸命ソフトウェアのエンジニアをかき集めているという状態である。
自力開発対オープン・イノベーション
今後の自動車会社の競争相手は、アップル、グーグル、イーロン・マスクのテスラなど、ソフトウェアの会社となる。日本の自動車メーカーは、ソフトを全部仕込んでモジュールとして行うのは苦手であるので、当然システムとして買ってくるわけであるが、購入先のシステムメーカーは日本のメーカーではなく、ヴァレオ、ボッシュ、コンチネンタルなど、ハードもソフトも持っているような海外のシステムメーカーである。その下請けとして、カメラ、マイコン、小型モーターなどのハードを作っているメーカーがおり、日本はこのハードに強い。つまり、自動車というのは真ん中に日本のシステムメーカーが入らずに、日本の部品メーカーが下請けになってくる。結果的に、日本はスーパティア2、世界の下請け国になってしまうというのが、自動車の世界でも起こりうる状態である。
日本の自動車メーカーは、これからソフトを勉強しなければいけない一方、グーグルやアップルは逆にハードを勉強しなければならない。グーグルやアップルは現在、ハードのメーカーを次々にM&Aで買っているが、まさにオープン・イノベーションである。地域開発をするのではなく、会社を買う、もしくはライセンスで作るのである。一方、日本のハードウェアのメーカーはソフトウェアの自前開発を一生懸命やっている。しかし、どちらが早く頂点に到達するかというと、皆さんもご理解の通りだろう。
そういった中で、例えば日産はシリコンバレーに研究開発センターを作り、NASAと提携して自動運転の車を開発している。トヨタは1200億円という投資をして、シリコンバレーにトヨタ・リサーチ・インスティテュートを作り、ヘッドにDARPA(国防総省国防高等研究計画局)のプロジェクトマネージャーを呼んできた。MITやスタンフォード大学と組んで(日本の大学と組まなかった部分が残念であるが)、人工知能開発を行っている。このように、日本の企業でもオープン・イノベーションを行っている会社もあるが、総じて言うと自力開発である。この自力開発と、オープン・イノベーションの競争が、今まさに繰り広げられているというところである。
勝又幹英社長
後半は、産業革新機構の概要と実際のベンチャー育成についての話である。
産業革新機構の概要
産業革新機構は、2009年に産業競争力強化法に基づいて作られた組織で、運営期間は15年と決まっているので、2024年には活動を終了する。株式会社という関係上、政府出資の2860億円、民間出資の140.1億円からなる約3000億円の払込株主資本に加え、政府保証枠が約1兆8000億円あるので、いわゆるファンドの投資能力という意味で言うと約2兆円強の規模を有している。革新性を有する事業に対して、付加価値を付けながら投資をしていくという活動が、現在7年目に入った。
この15年の運営期間の中で、特に比較的中長期のリスクマネーを供給して、投資事業の価値の最大化につなげることが目的である。短期的な利回りを追求するより、絶対的な富の創出に努力する。政府や民間からの出資を受け、時として民間企業、ファンドとの共同投資を努めながら投資をするわけであるが、同時に、経営や運営上のアドバイス、人材の紹介等々の計算型の支援も実施している。2009年以来、現在までに101件、投資総額8300億円の投資決定を行なってきた。産業革新機構というと、どうしても新聞を賑わせる大型案件ばかりを扱っている印象があるかもしれないが、実際にはこの100件の中約80件がベンチャー投資で、残りの20件強がいわゆる大型の事業再編投資、もしくは海外投資である。ただし、件数的に言うと約8割がベンチャーだが、大型の事業再編投資のほうが一件当たりの金額が大きいので、金額的には7~8割の部分が大型案件の再編投資、海外投資ということになる。
投資対象は、非常にベースとなる基礎技術の事業化からいわゆるベンチャー投資、さらには大企業からのスピンオフである事業再編、もしくは国内には存在しない製品やサービス、資源を海外に求める海外展開のための共同買収と、広範に渡っている。執行体制について、我々は約120名で運営しており、そのうち約80名がフロント、インベストメント・プロフェッショナルである。実際の投資の現場について、投資事業グループがいわゆる事業再編(大型事業再編、海外投資)を行っており、ここに約30名のプロフェッショナルが配属されている。次に、戦略投資グループは、いわゆるベンチャーキャピタル同様のベンチャー育成、ベンチャー投資を行っており、ここは約40名で構成されている。また、ポスト・インベストメントグループには、投資した後のバリューアップやイグジットを推進するプロが約10名配属されている。
投資対象となる事業化ステージについては、大きく4つに分けられる。1段階目が、知財もしくは知財ファンド等による先端的な基礎技術の事業展開、2段階目ではそれが研究開発を終えて製品化される。3段階目として、それがさらに大きくなって大会社からの事業再編、子会社の切り出しが行われる。そして、さらに海外にそれを打って出るというのが4段階目である。
ベンチャー育成の現場
我々は官民ファンドであるので、ベンチャー企業、もしくはスタートアップへの資金供給が最初のミッションである。特にその中でも、採算性を追求するというよりは、なかなか民間ベンチャーキャピタルもしくは民間の事業会社にとって比較的リスクが高いと思われる案件や、イグジットまでの道のりが長く、投資がしにくいと思われる案件を敢えて取りにいく。また、ゲームやアプリではなく、どちらかというと渋いものづくりや介入期間が長い案件にも、比較的積極的にアーリーステージから投資をしている。そして、最終的には一般の民間ベンチャーキャピタルが何とか普通の採算でも投資ができるところまで引っ張り、そこに優良な投資家を民間ベンチャーキャピタルとともに享受していくという流れも考えている。
次に、エコシステムにおいて大変重要な要素である人材の育成についてである。創業者、事業をはじめるアントレプレナーの人材育成及びその成長支援、成長を加速させていくベンチャーキャピタリスト、ファンドマネージャー、こういった人材育成も行っている。具体的には、オン・ザ・ジョブ・トレーニング及び各界の講師を招いて色々なナレッジシェアリングをしたり、時には志賀本人や私自身が講師で立つことで、かなりの割合を人材育成にも割いている。それが、最終的にはこの日本におけるスタートアップ、もしくはベンチャーのエコシステムの構築強化に繋がるよう心がけ、ベンチャーとお付き合いをしているというよりは、最終的な取引先になるであろう中堅大企業との共同紹介などを推進している。
実際に我々が投資をしているものづくり系、サービス系、健康医療系の代表的なものを一社ずつ選んでみた。一つ目はトライジェンスセミコンダクターである。これは、独自のデジタル処理技術を使い、デジタル音源をアナログ変換せずにそのままスピーカーに伝えるというための半導体を設計し、TDKやインテルと共同しながら最終的な製品化までもっていく。製品化の際、大手の音響製品メーカーのスピーカーのモジュールに組み込まれる会社への投資を2014年から行なっている。これは投資金額としては10億円という、ベンチャー会社への投資としては大きめのものづくりの投資である。最終的には、低消費電力や高品質な音響のプラットフォームをグローバル展開していきたいと考えている。そして、「フルデジタル化」という今までなかった音響分野に対して新しい市場を開拓していきたい。
次はサービス系で、スマートドライブという会社がある。現在、自動車の世界標準になっているOBD(On-board diagnostics)というデバイスがあるが、これを繋げるデバイスにした上で、最終的にはテレマティックス情報の収集および解析をしながら各種のサービスに役立てていこうという内容である。具体的には、アクサダイレクトと組みながら、最終的にはこのOBDから得た運転情報や走行情報などのテレマティックス情報自身をビッグデータ化して、この会社自身をオープン・プラットフォームとして新たなサービスのプラットフォームとしてしこうとしており、6.6億円の投資をしている。
最後は健康医療、ヘルスケア関係であるが、ステラファーマという会社がある。これは、癌に対する新しい治療法であるホウ素中性子捕捉療法(BNCT)に用いられるホウ素薬剤の薬事承認を目指して開発推進している会社である。会社自身まだ作ったばかりで、実際にはステラケミファ㈱と知財ライセンスの原料供給を受けながら、放射線を出していくハードウェアの部分については住友重機械とともにコンソーシアムを作った。これも支援決定金額としては35億円という、この手のベンチャー投資としてはかなり大きな投資をしている。この開発に当たり、エイメット、もしくは大阪府立大学などと共同研究開発をしながら、癌に対する新しい治療法であるBNCTの世界初の薬事承認実用化を支援していきたい。かつ、その過程においては、国内のアカデミアや異業種メーカーとのまさにオープン・イノベーションによる革新的な医療技術の開発ができないかとやっている会社もある。以上、ものづくり、サービス、健康医療についての代表的な投資例の紹介である。
ベンチャー育成の課題
一言で言うと、扱うベンチャーと、取引先もしくはイグジット先となる大企業、それからそれを支えるベンチャーキャピタル、このエコシステムの3大要素の有機的な連携が一つのハードルである。連携はしているが、有機的な連携が不十分な場合が多い。課題は色々あるが、1つ目はカルチャー面である。例えば、大企業においてオープン・イノベーションが会社全体にまだ浸透していないことが挙げられる。いわゆるNIH (Not Invented Here)症候群であるが、やはり自前主義が強い。また、大企業と取引をする際に、まずアカウントや口座がないと話さえ聞いてもらえない、アポも通らないといったことがある。次に、ベンチャーサイドの不備の面である。大企業との連携に当たって、十分な品質、体制を築けていない。最後にサポーターであるベンチャーキャピタルサイドにおいて、資金不足の問題や、アセットクラスと言われる投資枠を持っているところがまだまだ少ないという問題がある。これへの一つの解決策としては、ベンチャーキャピタルのパフォーマンスを上げ、投資家にアセットクラスとして承認してもらうことも必要だろう。
次に、大企業内での意思決定上の課題についてである。トップ・エグゼクティブの外部資源活用や、オープン・イノベーションの積極的な意識が組織的に未浸透という問題があるが、いわゆる社長はかなりこのオープン・イノベーションへの理解が進んでいるケースもある。しかし、社長にお話をして「この案件、ぜひご担当の方にご紹介ください」と言って担当常務あたりに持っていかれると、だんだんNHI症候群が頭をもたげてくる。つまり、トップの意識を変えるというよりは、次の次くらいにトップになる人の意識を変えていく必要を感じる。このあたりが我々が日々実際に向き合っているハードルである。 さらに、我々のもう一つの重要なミッション、エコシステムの循環、強化に向けての役割である。ベンチャーが陥りがちな課題への取り組み、解決において、傾斜問題がある。企業を新しく創業すること自体はすばらしいことであるが、自分が作った会社がかわいいがために、ステージが変わる際にも「自分が」と言ってなかなか人に任せない、チームの組成に対して快い返事を出さないということがある。特にアカデミア出身の場合には、どうしても技術信仰が強い。すばらしい技術を使った製品なら売れるのではという発想である。また、先述の大企業におけるNIH問題も大きい。しかし、それではどうしても死の谷にはまってしまうのではないか。また、シーズのところまで来たはいいが、知財の手当ができていなかったという問題もある。
もうひとつ、イノベーション・エコシステムのあるべき姿の中で、出口の多様化、イグジット戦略ということも大切である。米国では、ファンドもしくはベンチャー企業が最終的にイグジットするといった場合には、いわゆるM&Aもしくはトレードセールス、大企業への売却がメインであり、IPOがマイノリティである。日本の場合だとIPOが基本シナリオであるが、なかなかそのIPOまで行ける会社が少ないがために、最終的には創業者による買い戻しがメインになってしまっている。このあたりが先ほどのエコシステムの中のひとつの改善点であり、大企業の特にNo.2、No.3の方の心の岩盤をいかに砕いていくかが今後の課題になってくる。
官民ファンドとしてのミッション
日本以外の主要国においても、官民一体となってグローバルな競争力強化に取り組んでいる。代表的な例で言うとシンガポールやイスラエル、フランス等が挙げられる。しかし残念ながら、日本はまだ官民、もしくは産学官連携の取り組みでは出遅れている部分がある。一方で、産業革新機構は投資における財務的なリターン、ファイナンシャルリターンの最大化がミッションではないので、最大化のファイナンシャルリターンを追い求めつつも、最終的には日本の産業競争力の強化に通じるような投資を選抜的にしていく部分で国の政策と緊密に連携しているという点が、民間のベンチャーキャピタルとの違いである。そういう意味では投資リターンも求めるが、補助金とはまったく違う目線である。最近の事象としては、文科省の科学技術学術政策局に呼ばれた。ここは色々な補助金などを審査している局であるが、今まで補助金を出すか出さないかというブラック・アンド・ホワイトの議論であった。ただ、この補助金に投資効果という目線を入れ、投資効果の高い補助金とそうでない補助金、もしくは補助効果の奥行きの深い補助金とそうでないものを検討し、ブラック・アンド・ホワイトの中にグレーという考え方を取り込みたいということであった。そのためには、投資の現場にいる人間の目線を知りたいということで、局長以下50名に約1時間半お話をした。文科省さんがこのような考えを持っているということは、ある意味明るい話であり、日本のエコシステムに進化の兆しを感じた。
我々もミッションは、どの産業に投資を行うか行わないかという業界ごとのミッションではないが、今、比較的期待感も含めて重点投資領域としているところが3つある。日本でまだ少し遅れていると思われるIoTやビッグデータ、AIの領域。そして実用的なロボット事業の領域。もう一つは健康医療領域である。我々の意識としては、横軸に様々な事業、いわゆるセグメントを据えながら、縦軸をいわゆる投資のステージととらえている。上からアーリーステージ、ベンチャーステージとミドルステージ、それから大企業の事業の再編や、さらには海外投資といったものを、最終的には個別の案件を積み上げながら形成していく意識で日々投資を行っている。

| 生年月日 | 1953年9月16日 |
| 学歴 | |
| 1976年3月 | 大阪府立大学経済学部卒業 |
| 経歴 | |
| 1976年4月 | 日産自動車(株)入社 |
| 1990年1月 | 同社アジア大洋州事業本部アジア大洋州 営業部主任 |
| 1991年10月 | 同社アジア大洋州事業本部アジア大洋州 営業部ジャカルタ事務局長 |
| 1997年3月 | 同社企画室 主担 |
| 1997年7月 | 同社企画室 主管 |
| 1999年7月 | 同社企画室長 アライアンス推進室長 |
| 2000年4月 | 同社常務執行役員 |
| 2005年4月 | 同社最高執行責任者 |
| 2005年6月 | 同社代表取締役、最高執行責任者 |
| 2013年11月 | 同社代表取締役、副会長 渉外、知的資産 管理、コーポレートガバナンス担当 |
| 2014年4月 | 公益社団法人経済同友会副代表幹事【現職】 |
| 2015年6月 | 日産自動車(株)取締役、副会長【現職】 (株)産業革新機構代表取締役会長(CEO)【現職】 |


| 生年月日 | 1960年5月21日 |
| 学歴 | |
| 1983年 | 東京大学教養学部教養学科(国際関係論)卒業 |
| 1987年 | Master of Arts in Law and Diplomacy, Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, MA, USA |
| 2012年 | Stanford Executive Program、Stanford University Graduate School of Business, CA, USA |
| 経歴 | |
| 1983年 | 旧(株)日本興業銀行入行 |
| 1999年 | メリルリンチ日本証券入社 Global Principal Investments, Director |
| 2002年 | 日本みらいキャピタル(株)設立、取締役パートナー&CFO |
| 2007年 | ニュー・フロンティア・キャピタル・マネジメント(株)設立、代表取締役社長 |
| 2015年 | (株)産業革新機構代表取締役社長 |
| 資格その他 | |
| CFA(米国公認證券アナリスト) | |

<質疑応答>
質問1
いつもアメリカとの比較がされるが、アメリカと日本ではやはりカルチャーが違うと思う。例えばドイツのベンチャー事情はどうか。
勝又社長
私もドイツで投資をしたことはないが、大学の学生であるドイツ人留学生と議論したところ、ドイツでは教育制度が良くも悪くもすごくしっかりしているので、なかなか自分が専門に選んだものから飛び出て新しく起業しようという人はいない。ここは日本と近いのではないか。また、ドイツにおいてロケット・スタートアップというベンチャーキャピタルが、上場まではものすごい勢いで行ったが、物づくりではなくアプリやソフトに投資をしたため、後に失速しているという話も聞いた。これらを踏まえると、ドイツはものづくりにおいて非常に進んでいる部分もあるが、いわゆるベンチャー業界のエコシステムの部分はまだ日本に近いという印象である。
志賀会長
オープン・イノベーションという観点で見ると、ベンチャーのいわゆる産官学については日本と大分違っている。よく使われるデータで言うと、上場企業で年間に使われるR&Dの総額は日本は13兆円であるが、そのうち日本の民間企業が大学にお金を使っているのはトータル約750億円で、一件当たり250万円である。一方、ドイツの場合、自社開発ではなく産官学連携の中で協調領域を開発していく。そして、競争領域については自社開発を行う。例えば自動運転の3Dの地図の場合、あの中の悪いフォルクスワーゲン、ダイムラー、BMWが一緒になってノキアの下にある地図会社を3千数百億円で買収した。一方、日本のエンジニアは地図は競争領域だと言う。しかし、地図を作るためには莫大な投資が必要であり、そんなものはインフラなのだから協調領域として、それは産官学連携で一緒に3D 地図の開発を行えば投資効果が高いわけである。しかし、なかなかうまく行かない。産官学連携を協調領域ですんなりと行う部分は、やはりドイツが進んでいると感じる。
質問2
日本のメーカーが大学と共同研究をする際、日本の大学ではなく、アメリカの大学と研究するという話があった。また、日本の大学との研究費は一件250万円という話もあったが、何を変えれば日本の大学はこういう共同研究をもっと民間の企業とやれるようになるのか。
志賀会長
財源が国から出ないとなると、民間からどうやって出していくか。欧米の企業は、寄附と、民間との共同開発での資金が一緒になっている。なぜ日本企業が日本の大学と組まないかというと、最終的に技術課題の解決までコミットしてくれる大学としてくれない大学の違いである。
杉田亮毅氏
日本のビッグビジネスの場合、この環境変化への対応がなかなか大変で、非常にむずかしい局面にきていると感じた。また、新陳代謝を良くするためには、この競争力の落ちた集団を市場から出していく必要があるが、そのためにはある程度円高で踏ん張らなければいけない。つまり、円安コールを余り産業界も求めないほうがいいのではないか。メディアも我々も、そういうことは言わない方がいいのではないか。
坂東眞理子氏
コンテンツ産業やソフトウェアの話であるが、ハードも含め、官民協力することによって効果が上げやすい分野と、むしろそれぞれ個性を発揮して工夫をする方が魅力的な産業になる分野があるのではないかと感じた。また、日本の大企業は人材の宝庫と言われるが、実は人材の“死蔵庫”で、その能力を発揮するチャンスがない。この活躍の場が必要なのではないか。
秋元浩氏
企業が扱う製品について、コンシューマーやそれに近いものと、ライフサイエンス分野の医薬や創薬とでは、成功確率や必要な時間が違う。医療機器がちょうど中間だろうか。今後は、やはり日本としてこのような3つくらいの分野に分けて、どういう戦略でやっていくのかをそれぞれについて考えなければならない。
石田寛人氏
いかにしてこれから人材開発をやっていくかということが日本の将来のベンチャーの在り方と関わるのではないかと強く感じた。
柘植綾夫氏
日本の企業は変わらなければいけない。例えば「エコシステム」という言葉は昔からあったが、今だに日本流のエコシステムというのは全体の設計図というのが描けていない、共有化されていない。特に、大学の改革の中で、エコシステムに対して世界の潮流に遅れていると思うので、このあたりが見放されているのか。結果的に研究費の桁が2桁くらい違ってくるが、そうあってはならない。大学の方も、まだ潰されなければ大丈夫だろうとのんびりしているのではないか。
水野雄氏氏
ガソリン車がなくなるという流れに対してITの産業の方に直接話を聞いたことがあるが、本人も非常に心配していた。
相京重信氏
技術流出について、定年や活性化の若返り、リストラなどを行う際に、技術を持った人々が退職して、韓国や中国に週末になったら出かけていくという形での技術流出が一時期随分あった。このあたりのむずかしさを痛感した。
黒田玲子氏
一番遅れているのは大学の人の意識ではないかと感じた。企業は日々国際化の中で生きているが、大学人は自分の狭い研究分野だけ。国際化の視点をどのようにして普通の大学人にも浸透させるのが非常に重要だと感じた。
小島明氏
韓国は1998年の経済危機で、主要な産業が多くの分野で一社になってしまった。その結果、その一社が国内で独占利益を得て、海外に莫大な投資をした。一方で、日本には豊かな国内市場がある。それが日本の経済、産業の強さであるが、一社当たりの国内市場はむしろ小さくなっている。その危機意識が欠如しているのではないか。また、産業革新機構は政府の資金を基に活躍しているわけであるが、その政府の時代遅れな規制体制が、新しい意欲的な分野の妨害をしてはいないか。
丸山剛司氏
企業や大学のカルチャーの問題が多くあるが、M&Aや共同研究を進める上で、それぞれの組織の外に対する情報収集やアンテナの張り方が日本と海外でどのように違うのか。
志賀会長
日本の新陳代謝が進まないということについては色々な原因があるが、まずは、日本人経営者の抱え込み問題が結果的に新陳代謝を遅らせているという視点で提言書を発表したので、経済同友会のホームページを見て頂きたい。
また、参考までだが、例えばイスラエルは大学あるいは研究機関で基礎研究をされている。すぐ産業に役に立つかはともかくとして研究センターにも大学にも技術移転センターという民間の機関があり、大学の先生方が何を研究しているかを、そのセンターが見ていて、お金になりそうだと思うと、ライセンスなりスタートアップ企業を立ち上げている。また、政府の中にも経済産業省にチーフサイエンティストがいて、どの大学が何を研究していて、それをどういう形で政府が補助金をつけるかということを判断し、重点的にお金をつけている。そういう連携の仕方が非常に参考になる。もう一点、実際に世界を動かしているイノベーションは本当に基礎研究の部分である。コンピューターの上のプログラムの上でアプリケーションを作る世界ではなく、逆にプログラムの下のコンピューター・サイエンス、あるいは数学という部分が実際の世界のイノベーションを引き起こしている。産業界は最後に役に立つ研究を頼みがちだが、やはりもっと基礎研究の部分にお金を入れ、それが引いては産業に役立つということにしていく必要があるだろう。
勝又社長
最近の日本のエコシステムについて、メディアが使用している表現がある。1つ目がマイス(子ネズミ)で、ママ・パパの会社も含めたところが沢山ある。2つ目がエレファント、大企業とその子会社も含める。そして3つ目が日本に一番欠けているガゼルである。ピョンピョンと飛んで成長性の高いガゼル、これが伸びてくると、日本の成長率が上がる。その時の一つのハードルになるのが、やはりマイスを弱いものだから助けようと、エレファントが大きい顔をしてガゼルの進出を抑制している点である。このあたりのところについて、ガゼルを育てていくということが、問題解決のひとつの手段ではないかと考えている。
では、それをどのように育てていくのか。ベンチャーを支える役割は、ベンチャーキャピタリストとファウンダーの2つが担っているが、ベンチャーキャピタリストは教育によって育てられると思う。私が前職でベンチャーキャピタルをやっていた時、経験者を採用しようと思ったが、なかなか良い人材が採れなかったので、3つの条件を考えた。①大学でエンジニアリングのマスターを持ち②ITの事業会社への事業経験があり③ファイナンス経験無し――である。具体的には、約1年半に案件を2、3持ち、これをしっかりと行うと、世界で通じるベンチャーキャピタリストが育つ可能性がある。しかし一方で、ファウンダーは育てるのが難しく起業家教育は大変である。ただし、ここで間違っても「正しい起業家の作法」のようなものは教えないでほしい。なぜなら、そのようなものは存在しないからである。ただ、人生の選択肢として、あなたがそう思えば起業するという選択肢があり、そのためにはこんな方法やあんな方法がある、ベンチャーキャピタルという方々もいる。このエコシステムの理解を、実際に就職する前、人生の大きな決断をする前に提示すると、大きなエコシステムをする前に提示すると、大きなエコシステムが広がるのではないか。
また、ヘルスケアの話が出たが、産業革新機構は始動期間15年のうち既に7年が経ってしまっており、長期的な問題であるヘルスケアについては、解決に導くことはかなり難しいと思う。これについては、新しい仕組みの必要性を強く感じている。規制については、縦割り制度などによって、同じ経済産業省の中でも局による立場の違いを確かに感じる。また、日本と海外では情報の集積度の奥行きと厚みが違う。例えば米国では、スタンフォード大学裏のあるホテルのバーで、毎週木曜の夜になると関係者が一同に集まるイベントがある。そこには、とにかく起業したい人、それを見つけたいベンチャーキャピタリスト、それを助けたい弁護士やヘッドハンターなど色々な人がお祭り感覚で情報集積を行っている。そこは、違う文化や考えを持つ人々の衝突からなにか新しい物が生まれる環境でもあり、このような場所は米国のあちこちに存在する。これに似た情報収集の場が、日本でも渋谷や六本木で見られるようになってきたので、その流れを見守りたい。
第10回政策首脳懇談会 出席者 |
|
| 来賓・講師 | 志賀 俊之 (株)産業革新機構代表取締役会長・CEO、日産自動車(株)取締役副会長 勝又 幹英 (株)産業革新機構代表取締役社長・COO (随行者) 坂井 美帆 (株)産業革新機構企画調整グループ企画調整室アソシエイト |
| 会長 | 白井 克彦 放送大学学園理事長兼早稲田大学学事顧問(前総長) |
| 設立発起人代表 | 北城 恪太郎 日本アイ・ビー・エム(株)相談役 杉田 亮毅 日本経済新聞社顧問兼日本経済研究センター特別顧問 柘植 綾夫 科学技術国際交流センター会長 相亰 重信 SMBC日興証券(株)前会長 |
| 諮問委員 | 木村 節 リビア国経済・社会開発基金顧問 玄場 公規 法政大学イノベーション・マネジメント研究科教授 小島 明 政策研究大学院大学理事・客員教授、日本経済研究センター参与 角 忠夫 北陸先端科学技術大学院大学客員教授、むさし野経営塾代表取締役塾長 |
| 副会長 | 黒田 玲子 東京理科大学総合研究機構教授 野依 良治 科学技術振興機構研究開発戦略センター長 坂東 眞理子 昭和女子大学理事長 |
| 副会長兼専務理事 | 橋田忠明 日本経済新聞社・社友 |
| 理事 | 秋元 浩 知的財産戦略ネットワーク(株)代表取締役社長 石田 寛人 金沢学院大学名誉学長、本田財団理事長 西河 洋一 飯田グループホールディングス(株)代表取締役社長 (代理 佐藤 和広 同社執行役員) 則久 芳行 三井住友建設(株)代表取締役会長 (代理 三森 義隆 同社取締役専務執行役員建築本部長) 水野 雄氏 (株)旭リサーチセンター常任相談役 |
| 監事 | 丸山 剛司 中央大学大学院公共政策研究科特任教授、東京工業大学副学長 |
| 提携学会 | 河野 誠 日本MOT学会事務局長、(株)富士通研究所取締役R&Dマネジメント本部長 |
| 学校会員 | 林 明夫 (株)開倫塾代表取締役社長 |
| 副委員長 | 石田 正泰 知的財産委員会副委員長、青山学院大学法学部特別招聘教授 |
| 運営委員会 | 君島 章兒 三井住友建設(株)取締役専務執行役員 |
| 委員 | 安藤 真 東京工業大学理事・副学長(研究担当) 田中 守 東海旅客鉄道(株)執行役員総合技術本部本部長・技術企画部長 岩野 宏 住友電気工業(株)執行役員研究開発本部副本部長兼研究企画業務部長 兵藤 守 日本電信電話(株)研究企画部門R&D推進担当(技術渉外) |
| 事務局 | 田中 幸子 (一社)日本MOT振興協会事務局員 赤澤 眞理子 (一社)日本MOT振興協会事務局補佐、(株)ササオジーエス管理 |