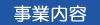サービス・イノベーション研究委員会報告
第14回 サービスサービス・イノベーション研究委員会(平成22年10月15日)
平成22年10月15日午後6時、東京都千代田区の日本記者クラブ大会議室において第14回サービス・イノベーション研究委員会を開催した。角忠夫委員長より開会の挨拶の中で「今日は、これまで検討したことに関して、最終ゴールに向けてどのような出口にするかを検討して、研究会の骨格を明確にする」との説明があった。
本日の委員会では、三井住友建設の吉田昌司氏から「無形資産価値評価と社内管理体制について」、小坂満隆副委員長から「サービス場とサービス価値」、JR東海の古橋智久氏から「高速鉄道の海外展開」と題する報告があった。
■第14回 サービス・イノベーション研究委員会での講演概要
1.「無形資産価値評価と社内管理体制について」:三井住友建設 吉田氏
建設業の立場から無形資産価値評価と社内管理体制について報告する。
建設現場、設計、技術管理部門、その後営業部門に所属し、現在はエンジニアリング本部に所属している。現在は、モノ(製品、建物)がない時点で客先に出向いていくことが多く、常に顧客に対してサービスを提供しなければならない立場にいる。
建設業では最後までモノは出来ず、出来るまでの間、無形な価値を提供する
『産業のサービス化論へのアプローチ』の中で角委員長は、製造業の代表的な例として「モノを作って、売って、その後サービスが提供される」と説明しているが、建設業では、最後の最後まで提供するモノ(製品・建物)は出来上がらず、有形な製品の概念が後半にしか登場しない。建物が出来るまでの間に「無形な価値」を提供可能な範囲がより広い分野であることを見ることができる。
つまり建設業のビジネスでは、サービスビジネス、無形価値の提供がすでに重要なテーマになっていると考えられる。
無形資産項目の要素をレベルごとに書き出してみると、例えば、人的資本であればプロダクツの段階では「製造スキル」や「マネジメント」の部分、サービスの部分では「販売能力」というように、ビジネスフロー上でそれぞれに無形資産要素が関与しうることが分かる。
重要なのは、どの部分が「差別化できる価値評価点」になるかを見定めることではないかと考える。
知的資本が企業にもたらす価値は業態や戦略ごとに得られる価値に違いがある
価値を評価することに関する先行研究事例をあたったところ、パトリック・サリヴァン著『知的経営の神髄』の本を見つけた。
「知的資本が企業にもたらす価値はケースバイケースであり、会社のタイプだけでなく、業態や戦略ごとに得られる価値に違いがある」とされ、価値の分類を行っている。収益やコスト削減などにつながって計量できる「直接」のものと、定量化できず直接の取引に関係しない「間接」のもの、さらに他社に対して積極的に発揮する「攻撃的」ものと自社内に準備される「防衛的」なものとで4象限に分けることができるとある。
このうち、防衛的なものと攻撃的なものの中に、どのような知的資本があり、具体的な価値が何であるかを列記したものとして、知的資本価値を表すマトリクス図が示されている。こうして知的資本の価値については具体的に分類されるが「関係資本」や「ノウハウ」といった領域は定量化しにくいものが多く、「価値を計るのが困難な領域」であるとされている。
自社における無形資産とその価値の評価を考察
こうした事例では概念的な話であるため、この分類手法を参考にしながら、自社における無形資産とその価値の評価を考察してみた。先に製造業のビジネスフローと比較した建設業のビジネスフローを活用して、どこに無形資産を活用しながら生まれる価値があるのかの俯瞰を試みた。
一般的な建設会社の流れは「営業して設計し、工事を受注して造る」という事業フローになるが、その中で建物を建てること以外で顧客に提供しているサービスの事例にどのようなものがあるのかをここに挙げた。例えば、営業段階では不動産情報提供がある。
不動産情報提供サービス
不動産会社が土地情報を持っていて、探している顧客は、そこで土地をそこへ求めることになる。こうした顧客はまず施設計画あるいは事業計画が先にあって、それに適した土地情報を幅広く探すことが多い。
こうした場合、建設会社を通して色々な情報を提供してもらうケースがあり、建設会社は企業が求める土地の大きさ、場所、機能をマッチングするために自社内で全国をつなぐデータベースから情報を提供するようなサービスに取り組む。
同様に設計レベルでは、3Dのコンピューターグラフィック(CG)を活用して建てる前に様々なシミュレーションを行うといったことがサービスビジネスとして挙げられる。ライフサイクルも含めて評価できるようなCADシステムが普及しはじめており、こうしたものの活用で顧客の事業リスクを低減することも可能となる。
VE提案サービス
工事の場合には、VE提案などがあげられる。建築図面や途中の計画図書は、最終形とかなり違っているケースも多く、顧客が最終的に望んでいるものも造っている過程で変更が行われる。こうした途中変更行為そのものがビジネスの中心的要素であり、そこでの施工VE提案は、日々行われていなければならないサービスである。
期待される価値:顧客の資産価値の向上や自社のブランド化
三井住友建設の「労務管理一元化」の取り組み事例を見ると、業種ごと組織単位ごと個人のスキルに依存し、重層化により把握しにくい職人の動きを、ITの活用で起こりうるリスクを低減し、高品質化を図ろうとする取り組みである。これは既存にあった人的資本やプロセスにネットワークという新しい価値要素を加えることで、他社に真似できない価値を構築している。
ここで期待される価値は、品質向上による顧客の資産価値の向上であったり、施工会社としては自社のブランド化であったりする。この収益あるいは価値の尺度は、無形資産価値の評価ができるようになると考えられる。
このように見ていくと、労務管理一元化であれば、既存にあった人的資本やプロセスにネットワークを掛け合わせることで、価値化されて評価するポイントが明確になり、“見える化”ができて尺度で測れる。
また施設群再構築提案であれば、人的資本とネットワークはもともとあり、その全体のプロジェクトを解決するための人材を集めたり、組織化したりといったプロセスを組み立てられるかどうかで、サービスの提供が可能かをマスタープランという形でお客様に提供できる。
価値評価を“見える化”する
これに対して、社内管理体制としてどのようなことをしたら良いのか、価値評価を“見える化”するのに、社内としてどんな取り組みをするかが、今後のテーマである。
考察の事例から、人的資本は社内に存在しているケースが多く、それにプロセスやネットワークといった知的資産部分の要素を掛け合わせていくことで見える化できている。どう見えているかは顧客側の話になるが「見せる側」と「見える側」とで価値のギャップがあり、その部分をリデザインして「見える化」できる。そこを誰がやるかということころが見えていない。
2.「サービス場とサービス価値」北陸先端科学技術大学院大学 小坂副委員長
最近「サービス場」と「サービス価値」を考えている。
サービスとは何なのかについて、亀岡先生の定義をもう一度見直した。先生は、「お客の総合価値は、製品価値とそれに付随するメンテナンス等サービス価値と、お客が個別に使う価値との総体のものだ」と定義している。製品価値が下がると、サービス価値や個別のユーザー価値を高めなければならなくなるが、サービスの定義は「人や組織がその目的を達成するために必要な活動を支援する行為」としている。
サービスドミナントロジックの価値は、使うときの価値で決まる
最近サービスサイエンス等で重要だと言われて注目されているものに、サービスドミナントロジック(バーゴ)というものがあり、従来の「製品を中心とした取引のロジック」と「サービスを中心としたロジック」とは違うと言われている。ここで注目したいのは、製品の価値はつくる人が決めるが、サービスドミナントロジックの価値は、使うときの価値で決まる。カスタマーがどういう状況で使うかによって価値が決まるとされており、顧客の存在を重要視しているというのがサービスドミナントロジックである。
こうした流れがあって、製造業のサービスに関わらずサービス価値が大切だと考える。
色々なサービスでも、サービスの価値は受け取る人の特性や時間、場所、企業によって違っている。サービスを必要とする状況と提供されるサービスとの関係性で価値が決まってくる。顧客は自分にとってサービス価値がどうなのかということに対価を支払う。いくら良い製品であってもそれがうまく使われないとお金は払わない。
よく言われるのは、キーエンスは製品を持っていて、プラスサービスエンジニアがお客にどう使ったらよいかを提供することによって、価値を上げてビジネスをうまくやっている。これはまさにサービスドミナントロジックである。ここで言いたいのは「サービスそのものや製品そのものに加えて、もうひとつどう使うかの『場』も含めてセットでサービス価値を考えなければならない」というのが主張である。
サービスも、お客との相対の関係で価値が決まる
ここで「サービス場」と言っているが、力を発揮するロジックは、物理の世界も人の世界も同じだと思う。電磁場は、電荷がいくら強くても場との関係で力が決まる。サービスもこれと同じで、製品やサービスがあっても、お客との相対の関係で価値が決まる。これがサービス場とサービス価値の基本的な考え方である。
例えば、サービスA、B、Cがあった時に、ポテンシャルの高いところにサービスを提供するとその価値が上がる。無形資産には2つあると考えていて「サービスそのものの価値」と「サービス場をきちんと認識していること」が挙げられる。マーケティングで顧客のことが良くわかっていることが重要で、何かというとこの場を認識しているということに他ならない。
サービスマーケティングと言われるが、人がどういう風なサービスに興味をもっているか、あるいはお金を払おうとしているか、といった場の分析をしている。
共創とICTの2つが重要である
サービス価値を上げるひとつの方法としては、双方のコミュニケーションによって相手のニーズがわかる、顧客とサービス提供者が一緒になって1つのことをやっていこうということで「共創」が挙げられる。
もうひとつはICTの利用であり、間接的にサービスの場の情報をすべて収集して、それによってどのようなニーズがあるのか、サービス場があるのかを認識している。
この2つがサービスの場の計測と把握で大事である。この2つをどう考えるか。サービス価値は2つの軸できることができる。ひとりの客に対して色々なものを組み合わせてニーズを満足させるのは「ソリューションサービス」で、共創が重要になる。
サービス場を認識して、そこでサービスを提供する視点が価値を上げる
サービスの視点を業務の中に入れると色々なことが見えてくる。ひとつはプロジェクト管理、もうひとつ共創、この中にもサービス的な視点で相手を支援すると考えると業務の仕方が変わってくる。従来のプロジェクトは、工数や人の機能あるいは技術の提供だけだったが、歩き回ることによってどういうサービスが必要かというサービス場をきちんと同定して、顧客の求める最大価値を提供していこうという考え方をする。サービス場を認識してそこで必要なサービスを提供するという視点が価値を上げる大事な点ではないか。
3. 「高速鉄道の海外展開」東海旅客鉄道株式会社 宮内室長 代理 古橋氏
海外展開の目的は、安全・品質の維持向上と技術開発コストの回収
JR東海の高速鉄道の海外展開の必要性は、大きく分けて2つと考えている。
まずは、高速鉄道関連製造業の市場確保による安全品質維持向上が挙げられる。これまで日本の高速鉄道業関連の製造業は新幹線の技術開発に牽引され、進化して新技術の普及が生み出す需要によって活況を呈してきた。そういった中で成熟された車両N700を中心とした東海道新幹線の技術は、成熟期を迎えている。今後の国内新幹線市場が限られていることを考えると、国内市場の拡大、活性化が期待できなくなると予想される。
海外展開を行うことによって、日本の高速鉄道関連製造業の受注規模を拡大し、国内メーカーの活力を高めることは、当社の東海道新幹線の安定的な運行を維持するためにも重要であり、市場拡大による製造コストの低減も期待できると考えている。
また当社は、国鉄の分割民営化ののちトータルシステムインテグレーターとして、自ら積極的に研究開発を行ってきた。これまで多くの技術開発投資を行っている。この投下した資本に対して最大の利益をあげるよう最大の努力をしていかなければならず、海外鉄道においてノウハウの提供や技術のコンサルティングといったフィービジネスによって、収益を得ようと考えている。
地球温暖化ガス削減の問題、環境問題への関心の高まりから鉄道建設の新たな潮流の変化
今なぜ海外展開を行うのかの要素のひとつに、海外鉄道建設の潮流の変化が挙げられる。地球温暖化ガス削減の問題に代表される環境問題への関心の高まりから、省エネルギー性に優れる交通手段として高速鉄道が世界中から注目を浴びている。
これまで高速鉄道整備が余り議論されてこなかったアメリカにおいても、オバマ大統領が2009年4月に全米高速鉄道構想を打ち出すとともに、米国再生投資法に基づく鉄道整備に対する80億ドルの補助金の支出決定など、各国で高速鉄道の建設が進められようとしている。こうして海外展開に大きな可能性が見出せることになり積極的に取り組むことになった。
何を輸出するかだが、開業から45年間乗車中の死傷事故ゼロという安全記録を更新中であり、定時性、列車の軽量化による省エネルギー性、これらは東海道新幹線が高速鉄道線の専用軌道を使用していることから発揮される純粋な高速鉄道のメリットであり、こうしたメリットはシステム全体で発揮されるものであり、このような高レベルなシステムをトータルで輸出することを前提としている。
一方、超伝導磁気浮上式鉄道、いわゆるリニアは営業運転に支障のないレベルに到達している。
SCMAGLEVと呼び高度な技術を有した最新のトータルシステムとして展開していきたいと考えている。現在、超伝導リニアによる中央新幹線計画を進めているが、その間に海外から引き合いがあれば、その機会を逸さずに取り組んでいきたい。

「高速鉄道の海外展開」と題し、報告するJR東海の古橋氏。
海外展開の対象路線について、トータルシステムの輸出先は、巨大インフラを投資する経済力がある国であることが前提である。
また、知的所有権の概念が確立し、契約の尊厳が社会通念として確立していて、かつ法制度が完備されていることが当社の権利をまもる上で必要であると考えており、こうした国、地域の中で広大な国土をもち、旅客輸送が自動車による地域内輸送と航空機による長距離都市間輸送の組み合わせが基本となっているアメリカにおいて、独立した純粋なトータルシステムが導入される余地があると考え、アメリカへの展開を重点に置くこととしている。
なお、海外展開の対象地域をアメリカに絞っているということではなく、こういった条件が満たされる前提で他国において将来的に対象となる路線がありうるとも考えていて、技術協力という形でもプロジェクトに関連するということもすべて排除しているわけではない。
海外展開の体制の説明
JR東海は、鉄道設備の建設、保有、運営の主体とはならないことを前提として考えており、商社・高速鉄道関連製造業とチームを組んでトータルシステムインテグレーターとしての役割をになうということを目標としている。こうしたことを追求するために、昨年7月に海外高速鉄道プロジェクトC&C事業室を発足させた。コンサルティング&コーディネーションの意味で、海外の高速鉄道の建設保有主体の要請を受けて、基盤構造物、軌道、信号設備、車両、運行管理、修繕補修などを含めたトータルシステムを提案し、建設が具体化した段階で日本の関連企業をコーディネートするとともに、運転補習のほか各種マニュアルの提供、要員の教育訓練など高速鉄道が安全安定的に運行されるまでの支援、コンサルティング業務を行う部門である。