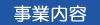コラム:ライフサイエンス分野における知的財産戦略
【第4回】 ライフサイエンス分野における日米の訴訟制度の相違(2011.5)
米国の制度に沿った訴訟戦略が必要
米国は訴訟社会と言われているが、ライフサイエンス分野で代表される売上高の多いブロックバスター製品であればあるほど、米国の制度上、4年目に必ず後発品(アンダー)による訴訟が提起される。
米国の訴訟制度は日本と完全に異なっていることから、米国の制度に沿った、あるいは米国の制度を利用した訴訟戦略が必要となる。
技術的判断を裁判官の専権にできる略式判決を求めることが上策
米国の訴訟制度の特徴として良く知られているのは陪審員制度であろう。日本でも裁判員制度により、一般の市民が裁判に関与するシステムが導入されてはいるが、日本の裁判員は刑事訴訟のみに関与し、米国の陪審員は特許訴訟のような民事訴訟にも関与するというような制度面の相違だけでなく、訴訟当事者の一方が陪審員を要求すれば、他方の当事者が例え反対であったとしても陪審員による裁判になる。
米国で外国企業が訴訟に巻き込まれた場合、よくホームタウンディシジョンになる所以である。
しかしながら、技術的判断は陪審員でなく裁判官の専権にすることができるので、略式判決(サマリージャッジメント)を求めることが上策である。
民事訴訟では陪審員の心証を自分の側に引き寄せるかを常に配慮する
一方、特許侵害に関する民事訴訟では賠償金の算定が焦点となるが、その算定では陪審員の果たす役割が非常に大きくなる。したがって、訴訟戦略としては、いかにして陪審員の心証を自分の側に引き寄せるかということを常に配慮する必要がある。
また、米国の訴訟では、誠実(good faith)と証拠が基本になることを常に留意しておかなければならない。法の精神に反するような行為をしていると見なされた場合は、懲罰的な罰則(3倍賠償)が適用されることも留意しておく必要がある。
ディスカバリー制度は、米国の民事訴訟を特徴づける最も重要な審理前手続
米国の訴訟対応で最も大きな課題のひとつがディスカバリー(discovery、開示手続き)制度である。
このディスカバリーは米国の民事訴訟を特徴づける最も重要な審理前手続で、審理の準備のために法廷外で当事者が互いに事件に関する情報を開示し、収集するための手続である。
このディスカバリーでは、当事者はその訴訟で審理の対象となる事項に関連すると考えられるすべての情報(メールなどの電子情報も含む)の開示が求められる。
ディスカバリーで要求された情報は、秘匿特権が適用されるもの以外は、すべて提示しなければならない。
日本では全くなじみのない制度であるため、ディスカバリーへの対応が適切でない場合が多々あり、そのために敗訴してしまうことが少なくないとされている。
開示されていない情報があった場合、その点が攻撃対象、不正な行為と見なされる
ディスカバリーでは、通常、膨大な量の情報が開示対象とされるため、その準備や処理あるいはそのための費用(数億円/年)が大変な負担となる。
ディスカバリーの対象とされたにもかかわらず開示されていない情報があった場合は、その点が攻撃対象となり、不正な行為をしていると見なされて、その理由だけで敗訴してしまうことになる。
また、ディスカバリーで提出した情報の中に矛盾があった場合も、その点が攻撃材料になる。
米国の企業は、ディスカバリーを想定した情報管理を行うことを基本としているが、多くの日本企業は、関係するすべての情報が提出を求められる可能性があるという考え方に基づく情報管理を徹底していないため、ディスカバリーで情報開示を要求されて、何か出し忘れていたり、あるいは不利な情報も保持していたりしてしまうことが非常に多いとされている。
不確かな記憶については、I don’t rememberなどと明確に答えることが肝要
米国の訴訟対応でもうひとつの大きな課題は、法廷以外の場所で質問に答えるデポジション(deposition、証言録取書)である。
デポジションは、米国内であれば弁護士事務所などで行われるが、米国の弁護士が来日して行う場合は、米国大使館あるいは総領事館などで行われる。
この制度に慣れていない日本人には大きな負荷となり、証言する人たちの間で矛盾があった場合には訴訟戦略として非常に不利になるので、通常、充分な準備(preparation, 予行練習)を行う。
特に、ちょっと賢いと思っている人(達)が推定で発言して大きな問題を引き起こすことが多々あるため、十分な準備が必要である。
不確かな記憶については、要は、I don’t remember, I don’t recall, I don’t know, と明確に答えることが肝要であろう。
弁護士に丸投げでなく、技術・知財・経営が判る優秀なコンダクターを置いて全体を統括すると良い − 米国で全戦全勝の企業もある −
ディスカバリーで種々の証拠等を収集し、デポジションなどを整理した後、争点整理や訴訟上の合意を形成するプリトライアル・コンファレンス(pretrial conference、正式事実審理前協議)を経て、正式な事実審理が行われることになるが、多くの米国企業のように担当者をおいて弁護士事務所に丸投げするのではなく、訴訟指揮者ともいうべき技術・知財・経営が判る優秀なコンダクターをおいて、全体を統括すれば米国での訴訟は恐れるものではないと考えられる(T社は米国訴訟で全戦全勝)。
ワールドワイドな知財戦略を目指し、自らが実践していこうとするのであれば、米国での訴訟を視野に入れておくことが必須である。
© Hiroshi Akimoto, 2011